『エンキョリレンアイ 』、『レンアイケッコン
』、『サンカクカンケイ
』の"恋愛三部作"が大ヒットを遂げ、恋愛小説の旗手として名高い小手鞠るい。無類の猫好きとも知られ、猫に関するエッセイや小説も数多く手がけている。
そんな著者の愛猫、プリンが召されたのは06年秋。その悲しみを振り払うべくエッセイ『愛しの猫プリン 』、また小説として愛猫の死を綴った『猫の形をした幸福
』を上梓するも、悲しみは深まるばかり……という中で、本書『九死一生』が誕生する。
「私には悲しみ続ける自由がある」、そう自作解説に残してもいる著者の思いの強さは本書のプロローグから示されている。
「もしもあなたが誰かを本気で愛したら、行き着く先には悲しみがある。悲しみ以外のものはない。(中略)なぜならあなたの愛した者は死ぬ。(中略)それでも誰かを夢中で愛したあなたは、報われる。なぜならあなたには、それ以上大きな悲しみは訪れない。あるいは、こうも言えるだろうか。残されたあなたの残りの人生には、もう、いかなる悲しみも存在していない。私にそのことを教えてくれたのは、一匹の猫だった。」
プリンの死を悲しみ続ける自由に対し「もう(これ以上は)いかなる悲しみも存在していない」とまで腹を据える著者。このプロローグから先、どれだけ悲壮感漂う"猫小説"が展開されるのか……と少しめげながらページを繰ると、それはすぐに杞憂だったことに気が付く。
主人公格の松川冴子、楢崎悠紀夫を中心とした人間たちの人生を、○匹の猫たち(ぜひ数を数えてみてください)がいきいきと駆け回る。著者の愛猫であるプリンが悠紀夫・冴子夫妻の飼い猫として最期を迎える場面から本章がスタートしていくが、そこでのプリンの描写も、またそれ以後出てくる猫や登場人物たちに悲壮感はまったくない(召される間近のプリンの様子に心を痛め、また死後も悲しみを引きずる冴子の様子が綴られているが、これはモデルが著者と仮定すれば物語として当然だ)。それはプリンの死を「悲しみ続ける」ことで受け入れ、「これ以上の悲しみも存在しない」と覚悟を決めた著者だからこその"猫(人)イキイキ感"なのは間違いない。
本章は1961年を皮切りに、2011年まで年月季節を切り取りながら全16章で構成されている。章ごとで冴子や悠紀夫など登場人物たちが悲しみや喪失感など様々な感情を抱きながら生きている様子が綴られるが、そこに現れる猫たちによって"救い"を得られて次章に繋がっていく。喪失感といっても、たとえば"愛"を失う場面としてカップルが罵倒しあうなど修羅場の描写があるわけでもなく、淡々と愛が失われた情景が綴られており、その心の隙間を埋めるべくやってくる猫の存在がとても頼もしく心地よく、また愛らしい。筆者(松本)は猫に対する理解は皆無なのだが、いわゆる"ツンデレ"な対応など猫の特徴が目の前であやしている(あやされている?)ように感じ取とれたものである。
本書を「恋愛小説」と読めば、そこには猫の愛らしさが浮かび上がる。「猫の本」と読めば、そこには猫が紡いだ大きな恋愛劇が姿を見せる。「恋愛小説とも、猫の本ともせず、両方を愛してほしい」と著者も奇しくも語ったこの『九死一生』。まずは恋愛小説と猫の本で反応してしまう人、とにかく手に取ってみることをお奨めする。タイトルの意味、そして悲壮なプロローグの真意は最後半で明らかになる。
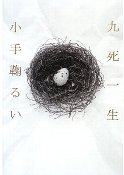
作者名:小手鞠 るい
ジャンル:小説
出版:小学館